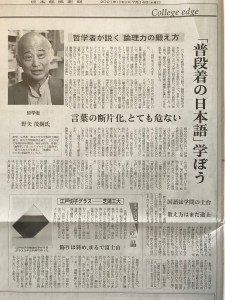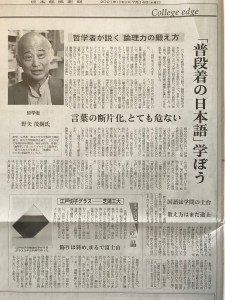
こんにちは、ちょっとお久しぶりになってしまいました。
気づけばもう五輪開幕直前です。まったく新しい参加体験が待ってますね。
さて、今回のブログは五輪とは関係ありません。
先日7/14日経新聞に掲載されたコラムを拝読して、
いままで自分の胸の奥にあったもやもやした違和感がなぜだかわかった気がした、
という話です。
私自身はIT弱者と呼べるほどIT操作に疎くSNSもアカウントは持っているものの
積極的に発信することはしておりません。
せいぜいがこのブログ程度です。
ただ、LINEについては家族/友人/知人/仕事のいずれの場合にも
必要かつ便利で積極的に使っております。
そのLINEでのやり取りにおいて特に感じていたのが、
グループトークでの瞬発的コメントの連打で意思疎通しているときでした。
1行だけの短いコメントに更に別の人が上乗せしていくコメント群。
絵文字やスタンプも交じってその時の空気感をめちゃくちゃ上手に表現する。
その応酬のテンポの良さ、素早い意思疎通、まさにSNS時代の会話なのです。
そして、そこにイマイチ追いつけない自分がいるのです。
しかも自分のコメントだけやけにテンポ悪く、長めのコメントになってしまう。
それが、この記事を読んで違和感のもとがわかりました。
哲学者の野矢茂樹氏が語るには、
SNSは「共感の原理」で動いているということです。
背景も前後もわからない中で短い言葉が流通し広がっていき、
その断片的な言葉に対し共感か反発かだけで済ませてしまう。
それは非常に危険なことだと。
共感は人間が持つ大事な能力であると認めつつ、
共感だけに頼る発言や行動はとてつもなく危ない。
論理で言葉をちゃんと繋いで議論ができる力を育まないといけないと。
そのためには国語力が大切であり、
論点を整理し明確に伝えていく力がますます必要になっていく、
ということです。
なるほど、と腹落ちしました。
テンポ良い言葉は共感を育む良い面とともに
深く論理的に理解するのは難があり(望まれておらず)、
正しく説明する力に劣る側面があるということを。
自分ではどうしても文章が長くなってしまう。
それはそれで自分のスタイルとして通していこう。
そんなことを感じた新聞コラムでした。
参照:日本経済新聞7月14日朝刊college edgeより
筆:黒沢