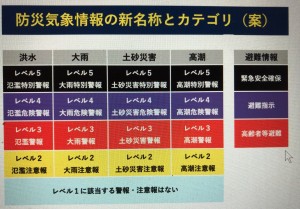2024.06.26
防災気象情報の言語化の難解
※図はフロントラインプレス作成記事より借用しました。
大雨や洪水など災害的気象状況が頻繁化している今日、
どんな注意報や警報が発報されたらどんな行動を起こすべきか、
分かっていそうで実は非常に複雑怪奇でわかりにくい、
というのが実態である。
その分かりにくさを解消しようと、国の検討会は数年に渡り会議を経て、
ようやくこのたび大きな指針が示された、と発表があった。
そもそもは、「大雨」「洪水」「土砂災害」「高潮」の4種に対し、
それぞれに表現が揃っておらず危険なのか警戒なのか特別なのか、
言葉を聞いただけでは切迫度も行動指針もわかりにくかった、ということだ。
それが今回、4種に対し、そろって4段階の共有用語を設け、
シンプルでわかりやすくした、というのが要旨である。
ここまで聞くと、それはよいことだ、と思うのだが、
その4段階の表現を聞いて唖然とした。
「注意報」「警報」「危険警報」「特別警報」の4段階である。
特に新しい視点は、警報と特別警報の間に危険警報を新設する、というのだ。
たとえば「大雨危険警報」や「洪水特別警報」というように。
ここでの問題は「危険」と「特別」ではどちらが切迫的なのであろうと感じるかだ。
どちらのほうが身に危険を感じるか、100人が100人とも「特別」のほうだ、
というならこの言葉の選択は正しい。
しかし、100人のうちたとえ10人でも危険のほうが危険と思うのなら、
この選択こそ危険なのではないだろうか。
もちろん色(黄・赤・紫・黒)やレベル数(2~5)と併用する、
とはいうものの、それで100%補完できるわけがない。
色は感覚的で個人によって感じ方が変わるだろうし、
数字はいくつが最上位なのかもわからない。
この検討には多くの有識者が集まり2年以上の月日を掛けていたそうだ。
検討会のメンバーの中でもこの結果に至るまでいろいろと賛否議論はあった、
とはいうものの、である。
検討会の「目的」は大局的に正しいと思うのだが、
その「結果=結論」とその経過での時間と労力を考えると、
高校生の夏休みの研究課題にも劣る気がするのは私だけだろうか。
なんにしても
日本の行政の時間と労力と結果の価値には絶望感が付きまとう。
そうつくづく思うニュースだった。
筆:黒沢