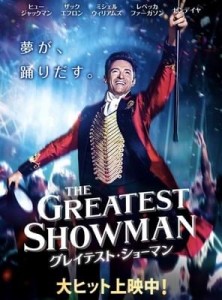昨年2月の月末金曜日から始まったプレミアムフライデー(PF)。
経産省が音頭を取って企画した消費喚起の運動だが、この2月23日(金)でちょうど1周年。
1年の振り返りを兼ねたイベント「プレミアムフライデー・サミット」なるものが、
東京の国立新美術館を会場に行われたので参加してきた。
プレミアムフライデー推進協議会の調査報告によると、
まず、現時点でのPF認知度は全国9割と非常に高い。
そして、1年間(全12回)のPF該当日早退率は全国平均11.2%
内訳は、大企業が16.4%、中小10.2%、零細10.2%
東京都が15.2%、三大都市圏11.8%、39道県12.0%
一方、消費喚起効果では該当日に関連した取り組みを実施した企業のうち、
約2割が売り上げ・来店客数が増えた・やや増えた、と回答。
つまり、働いている人の1割強がプレミアムフライデー企画の恩恵を受け、
消費喚起に取り組んだ企業・店舗の2割がプラスの影響があったということだ。
そのうえで、今後もプレミアムフライデーの文化定着のために活動を続けていく、
とPF推進協議会は宣言している。
でも、言い換えれば、9割の認知度がある中で1割の実施率しかなく、
消費喚起に期待して取り組んだ店舗のたった2割しか実際に効果がなかった、
ということとも言える。
しかも、クールビズやハロウィンの事例を参考に、
実際の定着までは数年掛かるものとしているが、本当にそれで定着するだろうか?
一言言わせてもらえば、
現時点での振り返りはもっと厳しく採点するべきであり、
結果を事実として正しく受け止め、抜本的なチューニングをするべきである。
そうでなければ、大金を使っただけで早晩行き詰り、忘れ去られるものになるだろう。
もともと「会社を早退して、余った時間を消費にあてよう」という、
役人の発想があまりに姑息すぎる。
早退して自分時間を作る、という提案は今の社会にはとてもいいことだと思うが、
この企画はそもそも厚労省ではなく経産省。
消費喚起が目的なのに、建前を美しくしているところにあざとさがある。
もっと素直に消費喚起したくなる本音のアプローチが無ければ、
成果には繋がらないのである。
早く帰ることが難しい、お金を使うことも難しい、という現代環境の中で、
プレミアムという名のもとに、どちらも解決できるほど、
働く人たちは気楽な心持ちではないのである。
プレミアムフライデーを「文化」にしたいのであれば、
もっと人のこころに響くように「真摯」に向き合ってほしい。
働く人はノーテンキではないのである。
そんな気持ちを持った1周年イベントだった。
弊社のプレミアムフライデーは、消費喚起ではなく、
早退推奨機会の「アーリーフライデー」として今後も進めていくつもりだ。
なんたって、堂々と早く帰ることができるのはうれしいものだから。
筆:黒沢